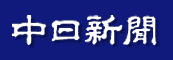 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
<湖になる古里>第1部(9)失われた民俗風習 一九八四(昭和五十九)年夏、民俗学者柳田国男とかかわりの深い成城大学民俗学研究所(東京都世田谷区)は、田中宣一教授(66)をリーダーとする調査団を徳山村に派遣した。 水没補償や集団移転での大量需要を見込んだ銀行員や住宅メーカーをはじめ、仏壇店までもが戸別訪問を繰り返していた。「聞き取りをしていると、玄関先で声がする。耳を傾けると金に関する話が多かった」 田中教授は、素朴な山村民の根底は変わらないが、ほかの山村とは何かが違うと感じた。「よそ者への警戒心は不思議とあまりなかった。ただ、お互いが疑心暗鬼に陥っているようで落ち着きがなかった。他家より少しでも有利に補償を得ようと“計算”を働かせるようになっていたのでは」と推測する。調査は、村が都会の烈風にさらされ始めた激動の時期と重なっていた。 調査団が最も注目したのは、信仰民俗の独自性だった。曹洞宗の増徳寺はあっても八割もの住民が信奉する浄土真宗の寺はなく、道場と呼ばれる建物があるだけで僧侶との接触は少なかった。 村内の過半を占める真宗誠照寺派の場合、四月と夏(八月末―九月)に福井県鯖江市の本山誠照寺から県境の峠を越えて僧侶が泊まりがけで巡教に来た。八集落の道場を順番に回り説教を行い、村人と飲食をともにした。「お廻り(オマワリ)」と呼ばれ、宗派の別なく村全体が浮き立つ“ハレ”の日だった。 田中教授は「多くの山村が過疎で民俗が消滅している中、徳山村は集団移転を控えていたために、一家離村は少なく民俗習慣が生き生きと残されていた」と振り返る。 移転後、各集落の神社は徳山団地の徳山神社に合祀(ごうし)された。しかし寺院は、増徳寺が移転したものの、浄土真宗の道場は二道場を残し解散。「お廻り」の風習はなくなった。 田中教授は「盆踊りとか伝統芸能とか一部を残すのは可能でも、便利な生活がどんどん入ってくる中で生活が変化していくのは仕方ない」と、民俗風習の維持の難しさに触れつつ「生活面での共同の労働をはじめ、地域の連帯は失ってほしくない。徳山村はそんなことを感じさせる村だった」。 【徳山村の民俗調査】 1935(昭和10)年前後に柳田国男の主導によって民俗学者桜田勝徳が行った「山村調査」が初めて。続いて、県教委が桜田らの指導で73年に調査報告書をまとめており、成城大の調査は3回目となる。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |