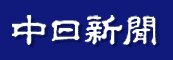 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
<湖になる古里>第1部(8)ダム屋魂、技術に誇り「徳山ダムは、私にとって子どものようなもの。いよいよ湛(たん)水が始まると思うと感慨深い」。半生をダム造りにかけてきた“ダム屋”三島勇一さん(62)=東京都練馬区=は、完成間近となった日本屈指の巨大建造物を前につぶやいた。 親子二代続けてのダム屋。父親も、土木技術者として北海道を中心にダムや堤防などの設計をしてきた。「おやじのように、大自然を相手に大きな仕事をしたい」と思い、迷わずこの道を選んだ。 大学院修了後の一九六九年に水資源開発公団(現水資源機構)に入社。二〇〇〇年の退職まで約三十年にわたって、設計や工事の現場監督などダム造り一筋の技術者人生を歩んできた。七三−八〇年には技術者として徳山ダムの現地調査を行い、ダムの図面を引いた。八五−八八年には、調査設計課長としてダムの詳細設計や事業費改定などに携わった。 徳山ダムは、高さ一六一メートル、堤の長さは四二七メートルで、貯水量約六億六千万立方メートル。貯水量は日本最大で、浜名湖二杯分の水が入る計算。土や岩石を材料に造るロックフィルダムで、ダムの「厚み」は最下部で約一キロになり、一般的なダムのイメージの「壁」というよりも「山」に近い。事実、ダム建設用に岩石を採掘したため、近くにあった小山が一つ消えた。 三島さんたち技術者陣は、「より完成度の高いダムを、より低いコストでつくろう」と昼夜を惜しんで試行錯誤を繰り返した。現場近くを通る根尾谷断層のことを考え、地震への耐久性が他のダムより高くなるよう設計した。 調査設計課長時代には、部下たちをロックフィルダム班と重力式コンクリートダム班に分け、どちらの工法がコスト面などで有利か徹底的に分析。結果、両工法とも実現可能でコスト面にもほとんど差がないことが分かったため、以前から計画を進めていたロックフィル式に決定した。 「日本のダム技術は世界最高峰」と、三島さんは自負する。戦後、欧米から招いた技術者から日本の技術者たちは必死に学び、日本のダム技術を世界最高水準へと押し上げた。日本の新規ダム建設はピークを過ぎたが、「今後は水が満足に得られない海外の国々のために、日本のダム技術を役立ててほしい」と期待する。 近年、無駄な公共事業の象徴とすら言われるダム。徳山ダム級の巨大ダムは、もう造られることはないという。だが三島さんは「地球温暖化や世界的な人口増加で、今後水需要が増加してダム待望論が再び持ち上がる可能性はある。今まで培ってきたダム技術を失ってはいけない」と訴える。 <ロックフィルダム> ダムの型式の一つ。コンクリートを使わず、建築現場周辺の土や岩石をうずたかく積み上げて造る。土で造った中心部の「コア」で水を止め、外側を岩石の「ロック」で支える。接地面積が大きく、岩盤が弱い地域でも造ることができるのが特長。他に主な工法として、アーチ式ダムと重力式コンクリートダムなどがある。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |