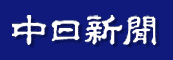 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
<湖になる古里>第1部(4)忘れられぬ水と空気「わしも徳山の家へ連れて行ってくれ」−。一昨年秋、体を壊して文殊団地(本巣市)の自宅で療養していた広瀬司さん=当時(86)=は、旧徳山村門入地区に残る家の様子を見に行こうとする妻のゆきえさん(86)に必死に追いすがった。 「いつもは『体に悪いからだめだ』と断っとったが、このときはどうにも行きたがってしょうがなかった」とゆきえさん。知り合いの車に乗せて一緒に連れて行き、二人で数日過ごした。文殊団地の自宅に戻って一月後、司さんは静かに息をひきとった。 「あの時、病気なのに無理して連れて行かなければよかったかな」。ゆきえさんは今でも後悔することがある。「だけど、『やっぱり家はええなあ』としみじみ言っとったんだ」 二人は廃村の三年後の九〇年、徳山村を出て文殊団地に移転した。家のあった門入地区は標高約四四〇メートルの高さにあり、ダム満水時の水面四〇〇メートルを上回るため水没はしないが、水資源機構は水没する、しないにかかわらず、全村民の移転を求めた。 「本当はな、おじいさんも私も村を出たくはなかったんじゃ。だけど徳山の冬は厳しい。周りの者が出て行ってしまえば、二人だけで残って暮らすことはできんかった」とゆきえさん。なかなか村を離れる決心ができず、移転を了承する書類に判を押したのも門入地区で最後の方だった。 二人は移転した後も、夏は毎年のように門入の旧宅で暮らした。「外の人間から見れば、『徳山村みたいな不便なところによく住んでいる』と思うかも知れんが、実は逆なんだよ」とゆきえさん。金銭収入を得ることは難しいが、川では魚が釣れ、山では山菜が採れる。何より水と空気がおいしいという。「人間にとって水と空気が一番大事。徳山はなあ、早い話、『人間の住むところ』なんだよ」 移転契約には移転後の旧家屋の解体が条件に盛り込まれ、水資源機構は契約に基づいて、門入地区の旧宅を解体するよう何度も求めた。が、二人は「最後まで徳山で暮らしたい」と、引き延ばし続けてきた。司さんが死去して、ゆきえさんはついに、秋の湛水(たんすい)前に旧宅を解体することに決めた。 「おじいさんが亡くなり、もう潮時だと思ってな。だけど、生まれ育った故郷、おじいさんと何十年も暮らした故郷は、やっぱり忘れようとしても忘れられん」とつぶやいた。 【門入地区】 旧徳山村にあった8集落の一つ。揖斐川本流である東谷に塚、櫨原(はぜはら)、山手、本郷(徳山)、上開田、下開田の6集落、上開田で東谷と合流する西谷に門入、戸入の2集落が並んでいた。離村が始まる前年の1983年の住民基本台帳によると最も人口規模が大きかったのは本郷の162世帯、485人。門入は37世帯、118人で、塚に次いで小さかった。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |