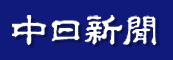 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
<湖になる古里>第1部(3)新天地でも村は胸に
「撮影で訪れたのは八十四回。試験湛(たん)水までに百回は数えたい」。民宿を経営していた藤野末広さん(52)=本巣市文殊=は、七年前から旧徳山村を撮影し続けている。新天地での生活再建。一家の大黒柱として多忙な日々を送りながら、ファインダー越しに懐かしさをかみしめる。 藤野さんが離村したのは一九八四(昭和五十九)年。この年、個別の補償契約が始まった。藤野さんは早期に移転した組だ。 「離村時には古里への思いもある程度整理がついていたし、皆を送り出すのがつらいからこそ、いち早く村を出た」という。 見通しがあったわけではない。「とりあえず村を出てから職を探そう」。三十一歳で妻子三人。岐阜市内の電設資材会社や運送会社などいくつか転職を重ねた。九八年から個人タクシーの運転手をしているが、「補償金があるので(職を替える)気安さもある。少々の赤字でもやってこれたので、甘い面もあった」。生活再建が容易だったわけではないが、補償のメリットもあったと振り返る。 徳山の生活も厳しかった。民宿だけでは生活が苦しく、夏場は建設作業に取り組んだ。工事のない冬に多くの人は失業保険でしのいだ。典型的な徳山の暮らしは「厳しいやりくりの連続」だった。 それでも古里への思いは格別だ。タクシーの客を写して喜んでもらおうと写真を始め、撮影の練習を兼ねて徳山を訪れるようになった。出来上がっていく巨大ダム、荒れていくかつての古里。対照を記録し続けた。 新生活の苦労は大黒柱だけが味わったわけではない。同じく早期移転組で八四年に長男、長女が住んでいた大垣市に新居を構えた安藤こなみさん(80)。離村時は昨年十月に八十三歳で病没した夫延さんと二人暮らしだった。 自然の恩恵に授かった生活は一変した。水道代や高額の固定資産税など何から何まで金銭の必要な都市生活。個人移転だったため周囲に知人は少ない。気心の知れた人に囲まれた暮らしが懐かしかった。 二十年以上の月日が流れ「いまは息子夫婦に囲まれて幸せ」と感じているが、古里を思い出さないわけではない。徳山の四季を歌った「徳山ブルース」。口ずさむと涙があふれそうになる。古里への思いに、離村時の早い遅いは関係ない。 <集団移転> 旧徳山村の全466世帯のうち331世帯が本巣市、揖斐川町、北方町にある計5カ所の造成団地に移転。残る135世帯が県内外に個人移転した。移転先は1974、75、83年の3度にわたる意向調査などを経て選定。補償契約の始まった84年以降、移転がスタートした。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |
