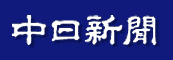 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
<湖になる古里>第1部(2)石一個さえ記憶に
児童文学者の平方浩介さん(70)=岐阜市上土居=は、一九七一(昭和四十六)年の村民大会の光景を鮮やかに記憶している。当時の平野三郎知事が「(佐藤栄作)首相と建設の確約を取り付けてきました」と声を張り上げると、約七百人の村民の間から「ウオー」と地鳴りのような声がわき上がった。「蛇の生殺しのような状態からの脱却、将来への不安、離村の決意−さまざまな感情が噴き出したのでしょう」 ダム建設計画は一直線に進んだわけではない。五七年の構想の発表、翌年の予備調査受け入れと続いたが、なぜか歩みはストップする。当初は村議会で反対決議をする一幕もあったが、具体的な計画の提示のないまま、構想受け入れが当然のような雰囲気が生まれた。水没を前提にすれば、長期的な施策も立てられない。「『沈むのだから金をかけてもしょうがない』と雪で壊れた家の日差しを直さなかった」。そんな村民もいたという。 十三年に及ぶ住民のフラストレーションは、村民大会で一気に解消した。二カ月後、村は建設具体化に向けた実施計画受け入れを承認した。以後、構想は一歩一歩進んでいった。 「建設そのものに反対していた村民はいなかったのではないか」と、平方さんは振り返る。「草木が風になびくように人が町へ町へと行く時代。他の村と違って支度金をもらって出られるのだから、まさに徳の山というのが村民の認識だった」。ダム完成を見越した暮らしは徐々に広がった。「『わしら後で補償金ぶら下げて行くで』と、跡取り息子だろうが離村させた」。平方さんは変わっていく村民の心を見続けてきた。 平方さんは中国・大連で生まれ、出生直後に村に戻った。戸入地区の分校の教師をしたこともある。地権者で、補償交渉の当事者でもあった。「補償の提示は対物の一辺倒。生活や心の補償も盛り込むべきだったんだ」。早期妥結を図る推進派に疑問を抱き、慎重な交渉を訴え続けた。その一方、生活再建のことを考えると、離村は早ければ早いほど、若ければ若いほど有利とも考え、推進派を批判し切れなかった。 苦い思いは胸にわだかまった。「セレモニーを楽しむ心の余裕はない」。村民総出の「徳山村おわかれ会」や閉村式には行かなかった。だが村への愛情は今でも変わらない。「(家の近くの)西谷の石一個さえ記憶に残っている。『あの場所でアユ釣りをしたな』などと考えると心が落ち着く」。古里はあせることなく脳裏に焼き付いている。 <一般補償基準> 各戸を対象にした家屋や農地の損失補償。旧水資源開発公団(現水資源機構)は1978、80年に村側の交渉窓口「徳山ダム対策委員会」に補償基準案を提示したが、低額を理由に村民が反発。膠(こう)着状態が続いた。その後、建設推進派の「徳山ダム対策同盟会」が発足し、83年に公団との間で交渉が妥結。翌年に慎重派の「徳山ダム補償対策協議会」が組織され、なお曲折を経たが、89年に全466世帯が移転契約を結び、古里を去ることが決まった。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |
