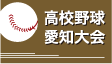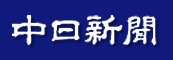 |
 |
| 東京新聞 | 中日新聞inしずおか | 北陸中日新聞 | 日刊県民福井 | 中日スポーツ | トーチュウ |
徳山ダム敗訴で原告団ぶぜん「時代錯誤だ」ダムの水はどこまで必要か−。国の水需要予測のあり方が争点となった徳山ダム訴訟の控訴審判決。1審と同じ「予測は不合理ではない」との判断に、原告側は「根拠がない」と不満をあらわにした。国は1審判決後になって予測を下方修正したが、ダム本体は計画通りにほぼ完成。2015年の全面稼働に向け、着々と整備は進んでいる。 「請求を棄却する」。03年12月の1審判決に引き続き、6日言い渡された控訴審判決でも、原告の訴えは退けられた。傍聴席からは「時代錯誤」と声が上がり、詰めかけた原告らはぶぜんとした表情を浮かべた。 「1審判決と実質的に何も変わっていない。司法による(行政への)審査がなされていない」。判決後、会見した弁護団長の在間正史弁護士(56)は半ばあきれかえった様子。1審判決をそのまま踏襲した高裁の「水需要予測が不合理だったとは言えない」との判断を「根拠がない」と切り捨てた。 争点の1つの治水面についても原告側は「ダムよりも、川幅拡張やしゅんせつなどの河川整備をした方が有効」と主張。だが判決はダム代替案についての判断を避けた。 原告団の上田武夫代表(75)は「このままでは、何のために裁判をしてきたのか分からない」と憤る。「もう一度私たちの主張を洗い直してもらうため、上告に踏み切りたい」と言い切った。 ◇ 徳山ダム建設に伴い離村を余儀なくされた旧徳山村(現揖斐川町)の村民は、控訴審判決を複雑な思いで受け止めた。村民の多くは訴訟にかかわってこなかった。 「やっぱり敗訴。思った通りだ。ダムの必要性の是非を論じる訴訟が住民の間で話題に上ることはめったになかった」と語るのは、旧徳山村戸入地区の住民だった広瀬静雄さん(70)=岐阜県本巣市。1審判決では、建設の根拠だった水需要について先細りが指摘されたが「洪水防止の役割はあるだろう。環境に配慮したダムを造ってもらえるよう願うだけだ」と話した。 旧村民にとっては、集団移転先の住宅の地盤沈下や、旧徳山村西側へのアクセス路の建設問題などが差し迫った課題として今も山積する。「村民の気持ちが置き去りにされたまま、判決などの司法手続きや、建設工事ばかりが進んでいく」。1審では裁判を傍聴し続けた旧村民の大牧冨士夫さん(78)=同県北方町=は、つぶやいた。 ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C) The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます |